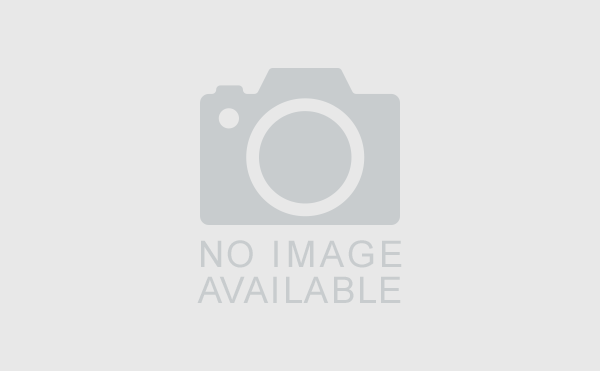【コラム】交通事故について
業務の中で学んだことや気づきを、コラム形式でまとめていきたいと思います。
今回は、平成27年版『赤本(下巻)』についてご紹介します。
◆「赤本」とは
「赤本」または「赤い本」とは、日弁連交通事故相談センター東京支部が編纂する
『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の通称です。
(参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html)
交通事故の損害賠償基準には、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
の3段階があり、一般的に「1<2<3」の順で高くなります。
赤本は、このうち「3. 裁判基準」の目安となる書籍です。
毎年改訂されており、「基準表などが掲載された上巻」と「講演録などを収録した下巻」が発行されています。
今回は、平成27年版下巻の中から、実務で参考になりそうな部分を取り上げます。
1.傷害慰謝料基準と判決の認定水準(中間報告)〔P81~〕
傷害慰謝料(後遺障害が残らないケガに対する慰謝料)は、入通院期間の長さに応じて算定される表が基準とされています(上巻掲載)。
この表には、
- 通常のケースに用いられる「別表Ⅰ」
- 他覚所見(画像等の客観的資料)がないむち打ち症に適用される「別表Ⅱ」
の2種類があります。
むち打ち症の場合は、通院期間だけでなく通院日数も考慮され、慰謝料額が低めに設定されます。
例えば、1月から6月までの6か月間、月1回(計6回)しか通院していない場合、実通院日数の3倍(=18日)を上限とする扱いになるため、「通院期間6か月」ではなく「通院1か月相当」として算定されます。
しかし、この中間報告では、実通院率が低い事案でも別表Ⅱの基準を超える裁判例が多くあるとされています。
したがって、通院日数が少なくても、実際の状況に応じてより高い慰謝料を主張できる余地があります。
「仕事などの事情で通院が間隔的になってしまった」という方も、ぜひ一度ご相談ください。
2.重要最高裁判例情報(最新判例研究部会)〔P127〕
ここでは、最高裁平成24年10月11日第一小法廷判決(判例時報2169号3頁)について解説されています。
やや複雑な事案ですが、要点をまとめると次のとおりです。
この判決と、平成18年3月30日第一小法廷判決(民集60巻3号1242頁)をあわせて読むと、
自賠法16条についても「非拘束説」が採用されたと考えるのが妥当です。
■ 自賠法16条とは
被害者が自賠責保険会社に対して直接請求できる権利を定めた規定です。
16条3項には「保険会社は告示で定める支払基準に従わなければならない」とあります。
では、被害者が訴訟で自賠責保険に請求する場合、
裁判所もこの「支払基準」に拘束されるのか――
ここが長年の争点でした。
学説では、
- 拘束説:裁判所も支払基準に拘束される
- 下限拘束説:支払基準を下回ってはならない
- 非拘束説:裁判所は支払基準に拘束されない
の三つの立場がありました。
平成18年判決は非拘束説寄りとされていましたが、
今回の平成24年判決では、15条に関する判断の中で「下限でも拘束されない」と明言されました。
このため、16条についても非拘束説が確定的になったと考えられます。
■ 非拘束説の実務上の意味
加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみのケースでは、被害者が「自賠責保険に対して訴訟で請求する」場面が生じます。
このとき非拘束説であれば、裁判所は支払基準に縛られず判断できるため、
- 支払基準より有利な場合 → 訴訟外で請求
- 支払基準より不利な場合 → 訴訟提起
といった戦略的判断が可能になります。
(拘束説では訴訟提起の意味がなく、下限拘束説では訴訟提起によるリスクがない。)
もっとも、この「支払基準」とはあくまで16条3項に基づくものであり、施行令2条の保険金上限には拘束されるため、活用できる場面は限定されます。
それでも、任意保険未加入の事案では非常に重要な論点です。
このような場合にも、ぜひ一度ご相談ください。